富山大学 研究者インタビュー#29
2025年4月7日12:00
清水 光治 先生
富山大学 医学系 特命助教
清水先生は、救命現場での豊富な経験と学術的な研究を基に、病院前救護分野の発展を推進しています。
近年、高齢化などの要因で、救急出動件数が増加の一途を辿っています。その結果、遠距離出動も増え、現場到着や病院収容にかかる時間が延伸しており、病院前救護(プレホスピタル・ケア)がますます重要視されています。清水先生は、水難救助隊・山岳警防隊や救急救命士として、災害現場の最前線で活躍してきた経歴を持ち、現在は大学での研究や教育を通してプレホスピタル・ケアの発展を目指しています。
「119番通報を受けてから病院に運び込むまでに行うプレホスピタル・ケアについては、これまでも研究は行われてきたのですが、大半は医師によるものでした。救急現場の最前線で活動している救急救命士自らが、病院前救護分野を研究する必要性があると思ったのが研究の道に進んだ理由です。また、救命活動の現場では『経験談』で語られることが多く、技術や知識が伝承されにくいという問題も感じてきました。アカデミックな分野では、科学的エビデンスを大切にします。経験談だけではなくエビデンスに基づく救命活動を研究し、救急救命士教育や救急活動プロトコルに落とし込んでいくことで、より質の高いプレホスピタル・ケアを実現したいと考えています。」
図1 救急自動車による救急出動件数及び搬送人員の推移(出典:消防庁「令和6年版 救急・救助の現況」)
プレホスピタル・ケアにおいては、蘇生ガイドラインに基づいた具体的な手順が示されています。たとえば、心肺蘇生の場合、一般的には「30回の胸骨圧迫と2回の人工呼吸」という手順が広く知られています。一方、救急隊員が実施する心肺蘇生では、連続した胸骨圧迫の中で人工呼吸を行うなど、より蘇生効果の高い方法も存在します。しかしながら、この方法は高度な技術を要するため、救急隊員が十分な訓練を受け、確実に技術を習得できる環境構築が必要です。清水先生は、医学教育学的なアプローチを取り入れた教育カリキュラムの開発によって、救急隊員の実践力向上を目指しています。
「日本の病院前救護分野はアメリカなどの諸外国と比べると歴史が比較的浅いため、救急救命士に対する教育技法や救命活動に関する研究は、さらなる発展が期待されています。そのため、より効果が高い技法を示すと同時に、確実にその方法を救急救命士・救急隊が習得できるよう、医学教育学的なプログラムを構築し、効果を臨床で実証できるように励んでいます。こうした活動を積み重ねることで、プレホスピタル・ケアを発展させていけたら良いと考えています。」
プレホスピタル・ケアには水難・山岳事故などでの救命活動も含まれます。水難救助隊・山岳警防隊としての活動や、潜水士資格もお持ちの清水先生は、実際の水難・山岳事故の現場でも数多くの経験を積まれてきました。
「水難救助事案では、発生直後の迅速な対応が非常に困難なケースが多く、119番通報後に現場へ急行しても、要救助者が既に深刻な溺水状態にある場合が少なくありません。また、救助隊が現場で救助活動を行っても、要救助者が心肺停止に至っているケースが確認され、その現状の改善が求められていると痛感しました。こうした背景を踏まえ、私たちはドローンを活用した新たな水難救助支援システムの研究に着手しました。」
図2 無人航空機(ドローン)を使用した水難救助手法の検証(清水先生ご提供)
研究では、水難救助法の一環として、ドローンに浮環を装着し、救助隊が到着する前に現場へ迅速に届けるシステムの検討を進めています。水難事故の際、救助隊が到着するまでの間に溺水者が浮環につかまることで、救命率が大きく向上することが期待されています。実際の実証実験では、救助隊が水中に入って救助を行うよりも、ドローンを飛行させたほうが、より迅速に救助活動を開始できることが確認されています。さらに救命率をあげるための取組みとして、ドローンを事故が発生しやすい場所の近くにあらかじめ設置しておき、遠隔操作で救急救助を行う方法も試みています。
ドローンに関して、他の用途への応用も検討しています。
「ドローンにサーマルカメラを搭載することで夜間や視界が悪い災害現場であっても要救助者の居場所を特定することが可能になりますし、AEDを搭載して現場に迅速に届けるといった用途も考えられます。さらに、スピーカーやマイクを備えれば、災害危険地域にいる方々へ避難の誘導を行うことも可能です。今後も、救命や災害対応の現場でドローンの利活用はさらに発展していくと感じています。」
清水先生の活動は、救急救命士の枠組みだけには留まりません。先生は、富山大学と新潟大学が共同で運営する『北越地域医療人養成センター』に所属しています。このセンターは、両大学の持つ教育ノウハウを共有して、地域を守る総合的な能力を持った医療人を養成することを目的としています。
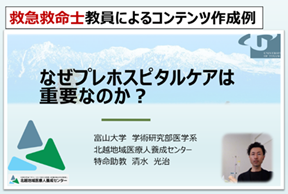 近年、医学生が卒業するまでに身に着けるべき能力に多職種連携能力があります。その対策として、救急救命士・看護師・理学療法士などと多職種協働できる能力を持つ医師を育てることも当センターの取組みの一つです。清水先生は救急現場での実務経験などを交えた講義を提供したり、わかりやすい教育動画コンテンツを作成・提供することで、幅広い知識を持った医師の養成に貢献しています。この取り組みが病院前と病院後を繋ぐ架け橋となればとお話していただきました。
近年、医学生が卒業するまでに身に着けるべき能力に多職種連携能力があります。その対策として、救急救命士・看護師・理学療法士などと多職種協働できる能力を持つ医師を育てることも当センターの取組みの一つです。清水先生は救急現場での実務経験などを交えた講義を提供したり、わかりやすい教育動画コンテンツを作成・提供することで、幅広い知識を持った医師の養成に貢献しています。この取り組みが病院前と病院後を繋ぐ架け橋となればとお話していただきました。
これらのプレホスピタル・ケアを考えるうえで最も重要なのは『教育』です。たとえ最適なプレホスピタル・ケア戦略が確立されたとしても、その効果を十分に発揮するためには、救急救命士がその戦略に基づく手法を確実に身に着け、実践できなければ意味がありません。
「救急救命士も含めた全ての医療従事者にアンプロフェッショナルを輩出しない教育プログラムを提供することが重要だと考えています。また、エビデンスに基づいた判断・対応ができ、エビデンスに基づいた技術で戦える救急救命士を育てるには、アカデミックな分野に携わり、自らの救命活動の未来を考えていく人材も、ますます必要になると考えています。近年では私のように研究の道に挑戦する救急救命士も増えてきました。」
医療・救急現場では、医療人材不足や高齢化による救急件数の増大など多くの課題があるとともに、それらに対応したテクノロジーの活用や医師のタスクシフトなど多くの対応が求められています。清水先生の『有益なものは積極的に受け入れる』というオープンかつ前向きな姿勢は、プレホスピタル・ケアを中心とした救命現場のさらなる発展の鍵を握っていると感じました。
共同研究等のご相談はOneStop窓口からお願いします。
(文責:学術研究・産学連携本部 コーディネーター 浮田)
富山大学研究者プロファイルpure https://u-toyama.elsevierpure.com/ja/persons/koji-shimizu
Researchmap https://researchmap.jp/ji-ko
北越地域医療人養成センター https://hokuetsu-dc.com/
富山大学医学教育学講座 https://sites.google.com/view/mededtoyama/home