富山大学研究者インタビュー#04
2023年9月6日
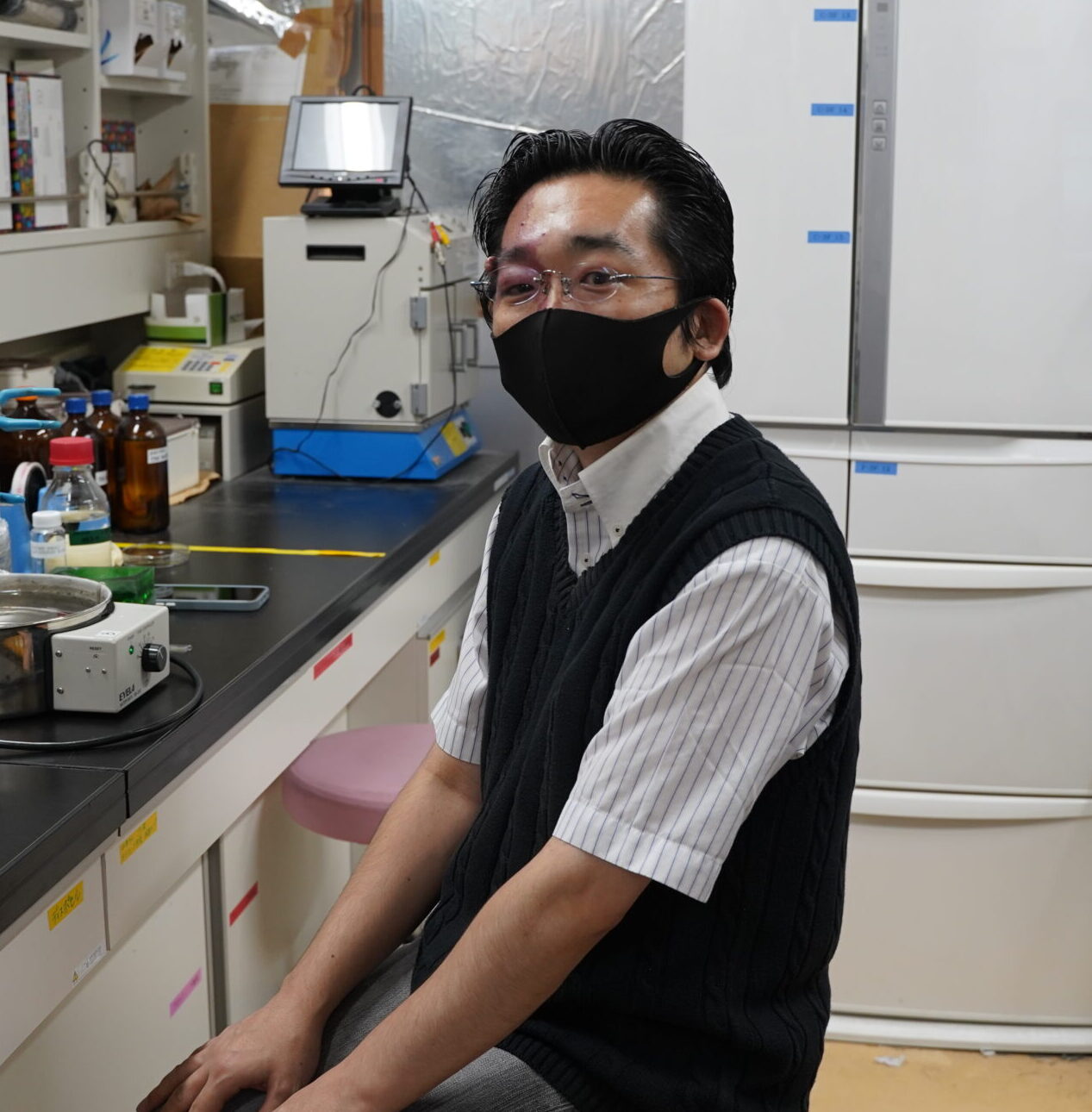
中路 正 先生
富山大学 工学系・准教授
中路先生は「人の病気を治すバイオマテリアルの開発」を目標に、
難治疾患の再生医療に貢献できる材料の開発・研究を行っています。
--研究内容について教えてください。
中路氏:生体活性材料の設計および開発です。元々合成高分子を用いた機能材料に関する研究を進めていましたが、生体高分子およびタンパク質を利用した研究を進めるようになり、バイオアクティブ材料の開発を手がけるようになりました。
富山大学に着任し准教授になった後、初めて学生を受け入れることになったとき、高分子に特化した材料開発をやりたいという希望があったことから、現在は、合成高分子を利用した研究・開発も、生体高分子を利用した研究・開発も両方進めています。
私は、生体現象は、全て化学と物理で説明できるとの考えを持っていまして、化学と物理が理解できていなければ、生体を、そして生体に対して良い材料の開発は出来ないと考えています。そこで、化学と物理を学んできた学生と一緒に研究したいと考えて、応用化学の学科を選びました。
学生たちがこの応用化学で何を目指したいかと聞いてみますと、化粧品を作りたいとか、環境に優しい材料などを作りたい等、マテリアルサイエンス寄りの研究・開発がしたいという話が多く聞かれました。
ですので、私が持っている知識やスキルと、学生たちがやりたい研究を、マッチングさせて学生の研究テーマを決めています。その影響から、研究室のテーマは、バイオアクティブとバイオインアクティブの2つの柱で進めるようになりました。
バイオインアクティブマテリアルは、生体に対して全く侵襲性がなく、生体内にいても何も悪さをしないようなポリマー材料のことを指します。これは、元々バイオアクティブマテリアル開発を行ってたことも有り、その対となるように命名しました。その後、いろいろな学生が配属され、学生のやりたいと考えていることが千差万別なこともあり、現在では、バイオコスメティックマテリアルや、バイオクリーンマテリアルの開発研究を加えた4つを柱にして研究を進めています。
--研究の特徴について教えてください。
中路氏:バイオアクティブの研究では、タンパク質を高分子にぶら下げるということが特徴になります。
タンパク質は、溶液中であれば拡散していき全体に広がる特性があります。よって、無駄があります。また、目的の細胞に効いてくれない、組織に効いてくれないことがよくあるので、タンパク質を高分子にぶら下げることによって、目的のところだけに効かせるような材料の開発を進めています。ちなみに、タンパク質をぶら下げることに対して、私はタンパク質アンカーリングと名付けました。
タンパク質を使う、高分子を使う、アンカーリングという3つの要素を基本として、様々な材料を設計しています。この基本要素と、学生がやりたいという研究に合わせるような形で、一つずつ研究テーマを立案しています。
毎年、バイオアクティブ・バイオインアクティブ・バイオコスメティック・バイオクリーンの4つの柱を軸に、約10個のテーマを考えて、そのうち1人1つずつ学生が受け持っていく方法で進めています。
--実際、研究を推進された中で、製品化に近いところまで行ったものはありますか?
中路氏:京大に在籍していた時に開発したバイオアクティブの培養器材は、某大手メーカーから発売され今も販売されています。
--特許料収入は入ってきますか?
中路氏:はい、ほんの少しです。なぜなら、開発したものは、特別に培養する時にしか、使われないからと聞いています。あと他に、自身が研究に携わって商品化されたものというと、某大手塗料メーカーのモノマーを使って作った機能性ポリマーコーティング剤があります。私は、その機能ポリマーの合成方法や性能評価、コーティング方法について研究しただけで、製品開発までには至っておらず、某大手塗料メーカーは、商品開発までつなげてくれる連携企業を探していたところですが、某大手塗料メーカーもモノマー開発だけではなく、製品開発まで自社で行うことを、ここ1、2年の間に決定したみたいです。もしかしたら、これから製品化に進むかもしれません。
特に、このバイオクリーン材料に属する研究ですが、花粉を吸着させない、花粉を逆に高吸着させて二度と逃さずに、そのまま捨てるというような、花粉の吸着制御できるような材料というポリマーのラインナップの開発を進めています。
私が商品化につなげてほしいと考えているのは、花粉を吸着する掃除機の集塵パックです。花粉吸着・低吸着のポリマー材料探索の研究を進める中で、一昨年、自らが花粉症になってしまいましたが、花粉症になってわかったことは、掃除機をかけるとものすごく辛いことです。
排気で、集塵パックから花粉や、また花粉が破壊されて出てくるアレルゲンが放出されます。そこで高吸着させて二度と逃さない、吸着しても花粉が壊れない、そういうポリマー材料が有れば、問題を解決できると考えて、高吸着であり花粉を壊さないポリマーを見つけました。
その後、製品開発を進めるための基礎のデータを全部出しました。それを某大手塗料メーカーが特許として出願してくれています。
--なるほど、それはすばらしいと思います。
中路氏:壊さずに吸着でき、二度と剥がれない材料をポリマーで作れるようになりましたので、集塵バックを作ってくださいと今は言っています。
--是非とも商品化して頂きたい。私も集塵パックを変えるときに、ダメになってしまうんです。
中路氏:そうですよね。私の目的は、人知れず人の役に立つような材料を作るということです。例えば、お医者さんにとって最強の武器になるような材料を作りたいと思っています。
私は、研究者自ら目立つのではなく、研究内容が注目されることが重要だと思っていますし、それを使ってくれるお医者さんが目立てば良いと思っています。
--何か目標になることはありますか?
自身が開発した基礎材料が実用化までこぎつけることですかね。例えば、美容と健康を両立できるような製品になったり、クリーン材料ということで役に立てること、例えば、アトピーやアレルギーを抑制できて、心地よい生活ができる、そんなふうな材料を開発するのが今のところ目標です。
引退するまでに、少なくとも5本ぐらいは商品化されたものがあるというのを目標にはしていますが、今はまだ某メーカーが商品化してくれた1つだけです。しかしながら、共同研究している企業から実用化まで持っていきましょうと言って頂いている研究が、2つあります。
--どこの企業ですか?
中路氏:県内企業のT社です。産学連携本部の高橋さんと大森先生が「こんな話が来てるからやってくれないか」ということでT社との共同研究を持ってきてくれました。
研究者にとって、研究を世界に発信するということは大事ですが、富山県の国立大学なので、富山という地域にも貢献しないといけないと思っています。
--ところで、先生は、現在、研究テーマをお持ちになられていますか?
中路氏:そうですね。私自身が進めるテーマは、元々3つ持っていました。しかし、学生から「ミーティングをしたいのですが、なんでそんなに忙しいんですか?」と言ってくるので、これはまずいと思い、学生に研究テーマを渡しました。その結果、自分の研究は1つになりました。今は、眼病の予防と治療を両立できるコンタクトレンズ開発に関する研究を進めています。
--そうなんですね。それは、どのような研究ですか?
中路氏:コンタクトレンズを着けていても眼病が悪くならない、悪化しないというような材料の研究になります。最初に思いついたのは「バイオインアクティブの高分子をコーティングする」という改良です。
そうすれば花粉もつかない、細菌もウイルスもつかない、つまり汚れないので、目が充血しない、タンパクがつかない、それで充血も収まるだろうと考えました。ただ、これは誰でも考えるだろうと。調べてみると様々な手法が提案されているみたいでした。
加えて、悪化している状態でコンタクトをつけて予防したところで、あまり意味がありません。それならばと「治す」という点も含めた改良を施すことにチャレンジすることにしました。
これは、バイオコスメティック材料開発において取り入れている「薬剤除放」と同じような発想で、コンタクトレンズから、定期的に薬剤が選択的に徐放される仕組みを搭載させることを検討しました。ただし、だらだらと徐放させることは誰でもできますし、誰でも考えそうなことです。
一方で、私としては、徐放に選択性を持たせることを考えています。例えば、眼病の症状で最も多く現れる症状である、涙の量が少なくなってドライアイとなった場合、水分がなくなるだけで、タンパク濃度、および塩濃度が上がるので、それを利用して、ドライアイの症状をトリガーとして薬剤徐放が急に早まるようなコンタクトレンズにするというアイデアを立案しました。
今は、特許も出願してもらったので、その論文を書いてる途中です。元々研究を始めた時には、某化学メーカーから「何か面白いことありませんか?」と聞かれ、「こんなことをやっています」と答えたら、それを共同研究にしましょうということになりました。
私が出したアイディアを、企業が具現化してくれています。私は、どちらかというと基礎の部分、薬剤徐放や、タンパク質吸着抑制、そういうところの基礎のデータを全部出すというだけになりますが、企業サイドでは、あとの商品化を受け持っていただくということになります。つまり、企業側では「こうすれば、安価に開発できる」というようなところを、受け持ってもらっているという感じです。
--実際、今までやられていた共同研究での役割でも同じようなことがいえますか?
中路氏:そうですね。私は、自分ができることと、できないことを認識しているつもりです。商品化まで持っていくためのコストダウンをきちんと考えてたとしても、企業からしてみたら全然甘いということになると思います。
そこは企業の人に考えてもらって、私は基礎の理論的なところや、絶対にこれは間違いないというエビデンス等を取るような研究を進めています。
ですから、応用研究という位置づけではありますが、基礎研究は絶対に疎かにはしないというスタンスでやっています。
--コンタクトレンズに関して量産化は近いですか?
中路氏:私が考えたやり方ですと、コストが非常に高いとの事。コンタクトを作った後で、高分子をコーティングするために溶液に漬けます。それは研究室内では簡単にできるわけですが、大量に行うとなると、すごく人手がかかるとの事です。企業の方ではそれをライン化する方法について検討しています。
私が研究の中で行っていた、溶液中で普通に重合するやり方ではなく、ベルトコンベアのラインにして光を当てること、つまり光重合によって、コンタクトレンズにコーティングするという量産化の検討をM社の方で行ってもらっています。
研究室レベルでは普通にガラガラ混ぜて、コーティングできても、それを企業に持っていくと、いくらお金あっても足りないよということになります。
いわゆるシステムエンジニアリングの分野における課題解決ですね、どれだけの機械が必要で、何千個とか作らないとダメとかいう話です。
このように、こちらでできること、できないことをきっちり話して理解してもらえること、人と密に相談しながら連携できるようにするのが最も大切と思っていまして、企業と共同研究する時には、そのような密な連携ができるように、その企業の人の、人となりを重視して選んでる感じです。
--どういうマインド、どういう姿勢の人と合いそうですか?
中路氏:そうですね。私がお断りした企業はいくつかありますが、そのような企業さんは、いかに売れるかということだけを考えておられるんです。売らねばならないという考えはよくわかりますが、それでしたら、企業だけで考えた方がいいと思っています。
論理などを追求した上で、その商品の確固たるエビデンスが欲しいと言われないと我々研究者は動けませんから、最初の面談やミーティングでそこを詰めます。
T社さんとは、3回か4回くらいミーティングして、お話を受けることになりました。
私たち研究者は、国民の税金で研究させてもらっているので、それをどうやって世の中に還元するのかというと、まずは論文という目に見える形で還元するのが最低限絶対に成すべきことである思っています。
論文という後世にも残る知識の詰め物を世の中に出さないと、私は話が始まらないと思っています。
論文は絶対書かないとダメですので、企業側がまずその考えを了承してくれないと困ります。企業さんの中には「いや、うちは論文なんか必要ないから」と言うところもありまして、お断りした経緯もあります。お互いが理解しあって譲歩できるという関係性がまず第一かなと思ってはいます。
--企業によっては、閉鎖的な企業もありますよね。
中路氏:論文は絶対いらないという企業の方が、まだ多いですね。
--それは、企業サイドとしては、論文は書いてもらいたくないからですか?自分の会社だけで保持しておきたいということですかね。
中路氏:こちらも論文は特許出願を終えてからと思っていますし、特許で守られているので、論文発表を拒むような問題はないと思ったりはしますが、どのような意図かは私には分かりません。
特許に出すとなると国内だけでも数十万円かかりますし、それを維持していくのに、ランニングコストが数百万円かかります。それを海外でも出すということになれば、ヨーロッパ以外にもアメリカも出さないといけない、中国も出さないといけない、ということになりますから、どんどんコストがかかっていきます。これを抑えたいからなのかもしれませんね。
特許でカバーしきれず盗まれること、改良して近い商品を出されることを考えると、論文は出されたくないとおっしゃる企業もありました。ただ単に、論文に時間をかけるのは無駄だと思われている企業もあると思います。
そういうことを言われると、私の立場からは辛いです。国民の税金で研究させてもらっている私たちは、どうすればいいのかと思います。理解していただけないところは結構あるように感じています。
--自分の会社の利益しか考えてない、売上しか考えていないという企業は、結構多いと思います。そういうところとは、やりづらいですよね。
中路氏:やりづらいのはあります。また、開発にかかる商品のアドバンテージ、売りになる部分を証明するためのエビデンスとなる基礎データ、ベーシックデータを出すことが、一番お金がかかります。
企業としても、そこにできるだけお金をかけずに、製造ラインなどにお金をかけ、コストを下げて、利益を上げようと努力されてると思います。そうなると基礎のデータは欲しいが、お金はかけたくない、ということになるのだと思います。
私の上司にあたる先生方の時代は、手っ取り早くそこは大学などに任せてという風潮があったため、かなり搾取されていたと思います。言葉は悪いですが、私たちのボス級ボスの世代の先生方は、企業との共同研究では、いわゆる企業の使いっぱしみたいな感じでやっていました。ですので、私が企業と共同研究しているのを、私を育てたボスは、企業の飼い犬になるために育てたわけではないと言われたことがあります。上の世代の先生方は、少なからず、企業との共同研究をあまり良く思われてないのだと思います。
ただ、私の持論としては、学者・研究者が製品開発まではできないと絶対に思いますので、そこはできないところとできるところを棲み分けて一緒にやるというのが、私は、一番効率がいいと思っています。そういう風に思うのは、上の世代の先生方が搾取されてきたからという思いもあってのことと思います。
また、その逆に、企業側も大学との共同研究をあまり良く思っていない世代の方は多くいるように思うこともあります。大学の先生の中には、研究費を稼ぐために、上手いこと企業を利用して、企業が本当に欲しいデータをあまり出さずにやり過ごすという方や、膨大な研究費を要求してくるといった方など、事例として少し耳にしたことはあります。
このように、いろいろと見聞きしたことからも、お互いがちゃんと密に話合い連携し合えるような人と人の関係を、特に信頼関係を、共同研究をする上で、第一に要求したりするのかもしれません。少し偏った考え方かもしれませんが。
企業と研究者は、対等な立場にあってほしいと思いますし、それを強く望みます。ただ、我々研究者は、国や民間財団などの競争的研究費を頂いて研究室を運営していますが、お金を稼いでくるというマネジメントはなかなかできません。
企業からしたら、企業は自分で稼ぎ自分で運営費を回しているというのをやっているので、お金、特に研究費に関して、国民の税金や財団の助成に頼っている私どもは、あんまり文句は言えない立場にあると、自身では思っています。企業は自分で稼いでますからね。
このような考えから、こちらからお金の話を持ち出すのは、実はなかなか難しいのが実情です。そのため、産学連携本部が前に出て動いてくれるのが、すごく嬉しい限りです。
本来、私はお金の話を持ち出すのが大嫌いなんです。研究費にこのぐらいかかるから、このぐらいもらえないなら出来ない、そういうことを本当は言わないとダメだとは思いますが、信頼関係の上で共同研究を始めましたという人に、なかなかお金のことは言いにくいものです。
これだけないと私はやらないよなどと言って、お金の切れ目が縁の切れ目みたいなことは言えないので。なので、そこは分担して、産学連携本部に丸投げしています。
契約の時に、費用はこのぐらいかかるだろうということを産学連携本部に伝え、「あとは産学連携本部さん、よろしく」というような感じで依頼します。
--なるほど、産学連携本部へ上手く依頼されているのですね。ちなみに、現在、どういう企業や組織との連携を求めていますか?
中路氏:バイオ材料はコストパフォーマンスが悪いと云われています。それは、売れるまでの先行投資が結構大きいためです。
バイオに近ければ近いほど、病気を治すところに近ければ近いほど先行投資は、億とか兆まで行きます。そうなると企業に耐久力がないと着手困難です。
バイオ企業というと、日本には色々あるかもしれませんが、耐久力があって何でも手を出せるのは、私の知る限りでは6社くらいしか思いつきません。それらの企業は元から原資があるので、失敗しても、それで会社が傾くようなことは絶対にありません。
そんな風に考えると、バイオ材料で共同研究は難しいかもしれませんが、一方で環境高分子材料や、化粧品の中でも薬用化粧品になるとハードルが低くなるので参入しやすい、共同研究に発展させやすいのではと思います。
もし、こんな材料を作りたいけれど、そんなエビデンスもないし、本当にできるのかわからないというのがあれば、話を伺って、私の力でなんとか出来るようであれば、共同研究をしたいものです。
実際T社は、現在、特殊細胞培養機材を商品化まで持っていこうとしていますが、元々T社は、普通のプラスチック表面への微細加工技術を持っている企業でした。
その技術を応用できないかということで、産学連携本部に声をかけられたという経緯があり、細胞培養で使えないかということで話が進みました。
構想から商品化までのストラテジーは率先して私の方で考えました。正直なところ、少し負担が大きかったのですが、基礎研究にも展開させまして、こちらとしても利になっているので、全然気にしていません。
こういうシーズがあるとか、こういうニーズがあってこういうの作れないかなど、そういう内容であっても、声がかかれば検討しますし、それが共同研究になることもあると思います。
私の特徴として、何にでも興味を示し、自身の知的好奇心に少しでも繋がることであれば、手を出したり協力したりしますので、結構門戸は広い方だと思います。
まずは自分ができることを対外的に発信して、企業側がその中から合致しそうな内容をピックアップしていただいて、産学連携本部に話が来るという形が一番いいかな、スムーズかなと思います。
--やはり、最近は、バイオ材料系の話が多いですか?
中路氏:そうですね。今やっている共同研究は、M社とT社の2つですが、どちらも企業さんが持つ技術をバイオ材料に展開できないかという話から始まっています。
それ以前は、N社やO社と共同研究していました。そちらでは、環境材料や汚れない防護材料・防護面を作るための高分子材料を最適化してくださいといった研究開発が多かったですね。そちらの方が商品までの道筋が近いというのはあると思いますね。
--企業としてみたら、基礎的なデータがあるとその商品の差別化にPRが営業としてできるということもあるのでは?
中路氏:今まで一緒に共同研究をした企業からは、確固たるエビデンスが欲しいということをよく言われました。そのためにデータ出して、論文出して、エビデンスを固めていくという流れで研究させてもらいました。
論文というのは、強い学術的な証拠になります。共同研究をした企業がたまたま良い企業だったのかもしれませんが、論文を書くことに肯定的な企業さんばっかりでしたので、私にとってもありがたかったというのはあります。
--企業の先の消費者側が、そういったものを求めていたのかもしれませんね。
中路氏:そうですね。企業の方々は、消費者が何を求めてるかを重視されて商品開発されますが、その求められてる消費者に、確固たる証拠を持って、「こうですから、これ良いんですよ」と言うためには、学術的な証拠が欲しいということはあります。
例えば、トヨタさんのようにトヨタ中研や、企業独自の研究所など、大きな研究所を持っていれば、そこが調べれば良いと思いますが、多くの場合、研究開発部があったとしても、そこまでしっかりとした研究を推進するというような部署ではないと思います。私は、それを担うのが、大学の研究室ではないかなと思っています。
共同研究では、企業の方々から教えてもらえる「社会はこういうものを求めている」という生の声を反映させて、こんなのがあったらいいんじゃないかと思える新しい研究の種を作れたらと考えています。
誰かがボソッと言った声や、広報などを通じて吸い上げてきた企業さんからのニーズを聞いて、最終的に商品になる元となる素材や材料を設計・デザインして具現化するのが、私たち大学の仕事なのかなという考えは持っています。
実際に、学生に研究してもらっている薬用化粧品では、汗が飛ぶと温度が下がりますが、その温度変化をトリガーとしてアトピーの皮膚炎を治療したり、悪化を防ぐようなような薬剤を放出するファンデーション素材を作っている最中です。研究基礎のベースを組み立てる研究をやっています。
これは、学会で女性たちが話している内容を聞いて思いつきました。「化粧品全然合わない、肌ボロボロ」と話している女性の中に知り合いがいたので聞いてみると、「予防ができて治せるような化粧品があればいいのに」ということでした。それが元となって、今の研究に繋がっています。
--なるほどですね。こういう化粧品でも、そういう要素が求められてきている背景があるんですね。
中路氏:そうだとおもいます。化粧品は飽和産業ですから、研究・開発しても、見向きもしてもらえないかもしれませんが。今や、ほとんどの化粧品は、既に分かっている効果がある素材を、配合を変えて混ぜて商品にするというのが一般的になっていて、ほぼ新しい素材・材料開発というのは無くなってきていると聞きます。なので、今やっている研究は、受け入れられるかどうかチャレンジになりますが、ニーズがある以上、チャレンジする価値はあると思っています。
今は昔と違い、ビルの中でぬくぬくと育った人間が多いので、ちょっとした環境の変化で肌がボロボロになってしまうそうです。昭和50年代から60年代に生まれた人間と比較して、ここ10年の子供のアトピーの発症率は8倍程度だそうです。
--そうなんですね。
中路氏:ですから、私と同世代は、アトピー発症者が激増した世代と言われて、多分80人に1人とか100人に1人がアトピー持ちと言われていますが、それが今では10人に1人くらいの割合になっていると聞きます。
私が子供の頃の1980年代は、回りにはそれなりに自然がたくさん有りましたし、それが今や、都会の中でしか生活していない人たちが多くいますので。皮膚疾患なんかは、高度成長に伴う負の遺産なのかもしれません。ただ、仕方ないといって指をくわえてみているだけではダメなので、それに対応するような材料・素材が必要だと思っています。これからの時代は、薬用化粧品や予防と治療を両方できるような素材という付加価値のある新しい材料が、世の中で必要とされ、どんどん出ていくのではないかと思います。
その最たる例がコンタクトレンズであったり、ファンデーション素材であったりするのだろうと思っています。
コンタクトレンズはM社がついてくれました。共同研究を進めるために、アメリカのコンタクトレンズ会社を買収したらしいですからね。
--あ、そうなのですか。
中路氏:M社さんがコンタクトレンズを出したところで、メニコンさんには絶対勝てませんよと言ったら、分かりました、半年待ってくださいと云って、半年後、コンタクトレンズ会社を買収したよってことを聞きました。
--どこを買収したのですか?
中路氏:アメリカの小さい会社だそうです。それでも業界で8位とか9位とかの会社のようです。共同研究をはじめる前から買収は狙っていたのでしょうけど、共同研究テーマを大きく広げようというために買収を本当に成し遂げたことには驚きました。そこまで本気ですということなのでしょうね。
--将来性を見込んでやっているのでしょうね。
中路氏:コンタクトレンズは、売れるという確信があるのだと思います。
コンタクトレンズ使用者として日本では、今1,500万人ぐらいいます。アメリカでは大体5,500万人ぐらいです。
2040年には、市場規模は1.5 ~ 3 倍になると予想されています。日本だけで、2人に1人がコンタクトレンズを装用することになります。
それにメガネかけている人が日本には、3人に2人ぐらいいますから、もっとパイがあるということになります。
また、アメリカではコンタクトレンズ使用者が多いという他に、アメリカ人は、コンタクトレンズを外さない傾向があります。
--昔、24時間着用コンタクトというのがありましたね。
中路氏:そうです。「ワンウィーク脱着なし」というのがアメリカのニーズです。「ワンウィーク脱着なし」と云っても絶対汚れるので、眼病が今までの3、4倍の速度で増加しているそうです。この薬用コンタクトレンズは、海外ではとても売れると思います。それを見越してアメリカの会社を買ったと考えています。
--商品化して広めていくという感じですね。
中路氏:コンタクトレンズに関しては、実用化まで貢献できる共同研究かと思っています。
薬用ファンデーションやその化粧品素材は、企業を見つけないと、研究のための研究になってしまいます。そのためにも、2年ぐらいで成果を出して自分で特許を取るか、企業を探して一緒に特許を取るという形で行きたいと思います。
--化粧品メーカーはたくさんありますよね。話にもっと食いつくような気がしますが。いかがでしょうか?
中路氏:そう思うのですが、なかなか難しいのです。コスメティック関連の学会で、以前発表した時に、「こんな材料があったら嬉しいんですか?」と企業さんに聞いたりしました。
企業の担当者からは「嬉しいです」とは言われましたが、こちらから「開発、一緒にしませんか?」と提案すると、「でも、コストが…」という答えで濁されてしまいます。先行投資することさえも躊躇している感じがします。
--業界全体的にそうなのですかね。
中路氏:聞きましたが、全く教えてくれませんでした。
--1社や2社だけではなくてですか?
中路氏:コスメティック関連の学会は、企業が特許化してくれた後の研究内容を発表することが多いので、ことあるごとに片っ端から聞いてみました。
K社などは、会社の研究所を無くすとの話を聞きました。研究開発については、大学なり海外の研究所などに依頼する様です。ですから、研究コストはほぼ無いみたいです。それで「よく新しい商品とか作れますね」と聞きましたら、もう飽和産業なんだそうです。混ぜてちょっと変えれば新しい材料になるのでということでした。
--なるほど、そうなんですね。
中路氏:その次のブレイクスルーの素材や商品が生まれないと、しばらくはみんな同じような商品ばっかりになるのかなと思いました。
--それは、日本だけですか?海外もそうなのですか?
中路氏:海外の化粧品メーカーについては分かりません。ただ、国内で研究所を残しているのは、某社くらいのようです。ですからそれ以外は、新規開発という点では止まっているのではないですかね。
研究開発を自社でもやらないようになったのは、恐らく化粧品業界が動物実験を完全に廃止するということを決めたこともきっかけの一つになっているのではと思います。化粧品開発に関しては、動物実験することは一切ダメになりました。動物実験をしたら、化粧品学会化粧品関連の学会にも出せませんし、商品化もできないと聞いています。
そんな状況ですから、安全性評価が完全ではない危ないものは出せませんので、既知の材料だけで手を替え、品を変え、混ぜたり捏ねたりだけという感じになりつつあるのではないかと思っています。
これを聞いた上で私のライフワークの一つに入れたのが、「動物代替法をきっちり確立する」ということです。
これは基盤研究になりますが、次の10年のテーマとして、あらゆる動物代替法を統一して、系統化させるような研究、材料開発を進めるつもりです。
基本的に、全部高分子ゲルを軸にする予定で、もし生体に近い反応が欲しければ、こういうタンパク質をぶら下げる、また生体により近い状態にしたい場合は、培養細胞と複合化するなど、いろいろな方法論を構築したいと考えています。
生体に近くなくても良いですが、硬さが同じなどの材料を作るための基礎的なベースとなるようなデータを向こう10年ぐらいで全部確立したいと思っています。それを基盤研究としてやっていこうと思っています。
--その取っ掛かりみたいなことをやり始めていらっしゃいますね。
中路氏:その取っ掛かりが、T社さんとのもう一つの共同研究で、透明模擬臓器の開発です。人体の硬さ、人体の臓器の硬さ、柔らかい伸び、伸縮などの形状と硬さが同じ、力学的な特性が同じというような透明性のある材料を作ります。
透明性があるので、例えば薬剤を注入した時に、その拡散状態を見たり、どこまで浸透しているかの中身が見えたりします。
中が見えるというのは、練習台とか評価には丁度良いので、そのような材料開発を進めています。動物代替品という意味では、それが取っ掛かりになるかと思っています。
論文まで仕上げたら、それを足掛かりに国の大きな研究費にチャレンジしてみようかと思っています。国の研究費を取ってきているというだけで、企業からの信頼度は上がります。
企業との信頼関係が破綻しない為にも、私は、企業から出資していただく研究費の倍くらいは、文科省、JST、JSPSから競争的研究費を獲得するスタンスでないといけないと思っており必死です。
更に、プラスアルファーで、間接経費も大学に入れないと大学が立ち行かなくなるのでというのは思っています。
--色々プロジェクトを立ち上げられていらっしゃていますが、現在どれぐらいのプロジェクトが進んでいますか?
中路氏:大きく分けて7つあります。それぞれ共同研究費または、国の研究費がついています。1つはインジェクタブルゲル、細胞を移植するためのハイドロゲル材料です。これに関しては基盤研究Bで支援していただいています。
コンタクトレンズはM社から共同研究費をいただいてやっています。
模擬臓器の開発も、T社から研究費が出ています。この研究開発では、微細加工表面上で選択的に細胞を培養したり、今流行りの2.5次元培養を簡単にすることを考えています。
3次元培養は細胞培養を凝集して培養させますが、2次元バイオは平面培養です。どちらもデメリットがあります。そのデメリットを解消するために注目されてるのが、2.5次元培養です。表面に加工を入れて細胞が3次元でもなく、2次元でもなく培養できるというようなものが一番簡便に培養できて、生体内の挙動に近いようなデータが得られるのではないかと言われています。
その2.5次元培養を簡単にする、簡単に誰でも導入できる、どんな研究者でも導入できるような形にするという目的を持って、T社さんで微細加工の培養機材を実用化することを考えています。
その他、私が科研費からお金を取ってきている中に、軟骨人工軟骨組織を外で作ってそれを移植材料にするというプロジェクトがあります。
軟骨組織を構築するというのが主な研究ですが、その研究に関連して、単一細胞種だけにするというカラム材料の開発も進めています。特定の細胞と選択的に相互作用するオリゴペプチドを高分子状にぶら下げて、その高分子をシリカビーズにコーティングしてカラムに詰めて、そのカラムに細胞を流すと、その特異的に相互作用する細胞だけが捕まって、それ以外の他の細胞が抜けていくといった材料です。これで細胞純度をあげて、軟骨組織構築に用いるというのが目標です。
7つのプロジェクトは、研究費を支援していただいて動いています。他は、研究費はついていませんが、研究費を取れる可能性や誰かが興味を持ってくれる可能性があるような研究テーマを学生5人に進めてもらっています。
学生には、これからの世の中は、例えば9時から17時までのように時間を決めて、限られた時間の中で、いかにして成果を出すかということを考えなさいと言っています。
それを守らせようしているので、なかなか2つ、3つの研究を担当させることが難しいです。なので、今動いているテーマは、学生1人だけ、自分は2テーマやると言ったもので、全部で12テーマですから、私を含めると13テーマあります。そのうち7テーマは、研究費がついている状態です。それ以外のテーマは、研究費は申請していますが、取れるかどうかがわかりません。まだ、成果もそこまで多くない萌芽的な研究であるからです。
一方で、民間財団の研究助成では、成果が出る可能性が非常に高いものしか申請を出していません。バックグラウンドとなる研究が有ったとしても、アイデアだけで申請が通ったことが一度もないからです。
中には、私の花粉研究のように、構想だけでアプライしたところ、採択を頂けた財団もありますが、一度切りです。花粉の研究は、財団に助成して頂き研究を続け、それで成果が出始めたところで、他の研究で御一緒頂いたO社が、共同研究で続けましょうと言ってくれました。実用化はO社が頑張りますと言ってくれています。
しかし、なかなかありませんよ、そんな構想だけでお金をくれるような足長おじさんみたいな人はいないと思います。
--ある程度形になっていないと難しいのですね。
中路氏:ペイバックがあるというところまで行かないと、なかなか難しいかもしれせん。そんな印象を持っています。
--とはいえ、基礎研究というところを先にある程度予想して、見据えた上でやらないといけませんね。
中路氏:そうですね。
--企業が欲しいと思っていたら、もうそれは量産が近いわけですよね。もう少し先を考えないといかんですね。
中路氏:企業が欲しがるということは、ビジネスチャンスがあるということになりますから、その出口を考えて研究を考えるというのは結構ありますね。
うちの研究室では、絶対に「戦略を持って、出口を見据えて基礎研究を立てる」ことを日頃から言っています。
学生には、発表する時に、緒言の3枚のスライドの中で、最終的な出口はどこにあって、その出口のためにどのような戦略を持って研究を進めているのか、今やっている研究は出口にはすごく遠いがちゃんと出口を見据えてやっていますと説明できるようにしておきなさい、ということを言っています。
--なるほど、それは大事ですね。
中路氏:ほんとに大事だと思っています。それがないと、もしうまくいきデータを出した時に、企業にアピールしようと思っても、その出口を元々考えてないとそれどこで使えるの?ということになります。研究のための研究にならないように、出口はちゃんと設定するように指導しています。
もしその出口に直接的に行かなくてもどこかで使えるかもしれませんし、近いところで、ということも考えながら研究テーマを立ててます。
--今の研究開発において大変な部分について教えてください。
中路氏:研究に関して難しいと思ったことは、あまりありません。壁にぶち当たった時に他の方法を探したり、他の手法からアプローチを変えたりするのは、楽しいのでおもしろいと思うことはあります。
一番難しいと思うのは、学生の教育です。私自身は、予想できるところを全部予想しながら研究を進めますが、今の学生さんは、先が見えないと、特に答えがないと不安なのだと思います。だからといって、こちらが予想や答えを教えてしまうと、学生は、何も考えなくなりますし、それに近いデータしか出てこなかったりするのをすごく恐れています。
真っさらな気持ちでやったらいいよと言っています。自分で予想することと、指導教員から聞いて予想することの大きな違いは、それがさも本当かもしれないと考えてしまうことです。かなり心のバイアスがかかるということです。
それを避けるために言わないようにしていますが、言わなかったら「データが出るかわかりません、しんどいです」みたいなことを言われます。どうフォローしようと考え、「こちらで予想している結果はあるからやったらいい」と、何かしらポジティブなデータはあったみたいなことは言いますが、全部こうなる可能性があるよとかマインドコントロール的な言葉になるようなことは、絶対に言わないようにはしています。研究って答えがないことを導き出そうとしているにもかかわらず、それがしんどいと思うという学生が大半です。それが大変ですね。
自分で考えるのだったらいいのですが、なかなかそこまでの知識がついてないとなると、答えばかりを欲しがってしまうみたいですね。
また、企業と共同研究して、それに学生が興味あるといえば、学生の1テーマにしますが、企業から求められるスピードと、学生のゆっくりやりたいというスピードがあり、それをマネジメントするのは、すごく大変です。
何につけても学生です。多分それ以外悩みはありません。いかにして気持ちよく仕事をして、気持ちよく成果出して、卒業してもらうかという辺りを考えるのに、一番気を遣います。
--その辺は、学部生も学院生もみんな同じようなマインドなんですか?
中路氏:そうですね。たまに昭和的なマインドの学生もいます。うちのドクター2人なんかは、昭和的なマインドですからね。現在のコンプライアンス的には完全にアウトだとおもいますが、「24時間あるのに8時間では研究なんか終われない」と言う学生が周りにいると、妙にほっとします。
--そういう人がいるといいですね。
中路氏:安心はしますが、だからといって、ダラダラやると世界に負けるからそのマインドは変えなさいとは言っています。
--研究室には留学生もおられますか?
中路氏:今は、留学生はいません。インドやマレーシアのポスドクはいましたが、現在、留学生は採用していません。何件か書類選考後の面接はやりましたが、絶対ここでやりたいというマインドではなかったので、他を当たってもらいました。
--海外の留学生の方がマインドがアグレッシブなのかなと思いました。
中路氏:そうかもしれません。中国人の留学生は、アグレッシブかもしれません。実際うちのポスドグでいた留学生は、アグレッシブどころの話でなかったですね。成果、成果、成果そういう人間だったので。
私の個人的な見立てですが、今の学生は、周りの雰囲気に流されて、何かしら焦っている世代という風にとらえてます。といいますか、今は膨大な情報で溢れていますので、その情報に振り回されて、自分の確固たる信念があまりない学生が多いと、そんな風に思っています。
例えばですが、研究室、特に私は、企業との共同研究を推進する方なので、某企業はこういう人材を求めてるなどの情報を持っていることが多いです。学生は、そういう意味で、アグレッシブに企業と共同研究している研究室を選んだりしているという話はよく聞きます。情報が溢れかえっている時代なので、どの情報が自分にとって良い情報なのかが分からなくなっているのではないかなと思いますね。そういう情報を取捨選択するのを手助けするのも、教員の仕事になりつつあるのではないでしょうか。
学生にとっても、企業と共同研究して社会に触れていることは、良いことだとは思います。ただ、企業が求めるスピードは早いですから、それについていかせるも大変です。
学生にそのまま伝えると気が滅入ることがあるので、「別に企業が求めているのではなく、私がちょっと早く知りたいのだけれど、どうかな?いけそう?」というような感じで相談する形を取ります。結果が出たら、「それは、企業がほしがっていたデータなんだよね」という感じに、結構気を遣っています。
--そうなんですね。
中路氏:ですから、学生のことやこちらの状況もきちんと理解してもらえる企業さんとやりたいですね。学生は駒ではないので。「お前ら駒だ」と言ってた我々の学生時代とは違いますので。
--資金調達で苦労はありますか?
中路氏:金策では、提出する1ヶ月前などは、私もしんどいと口に出しますが、それが普通なんだと思っています。
取れないと辛いっていうのはあります。基盤Bも2回落ちてます。取るのに3年かかりましたので、その時は非常にしんどかったというのはありますが、何かしらの助成金や共同研究費がありました。
私は今のところ、研究者になって1年間お金がないと言うのを、1年しか経験していません。国の研究費以外にも、共同研究費はいろいろとつながりがあって続いてるので、振り返ってみれば、1年しかないんです。有難い限りです。毎年、科研費は出さないといけませんが、大変さという意味では、全く上位ではなく、研究者として普通だと思っています。
研究を進めていて、どうやって実用化に持っていこうかというのを考えるのが一番大変だと思っています。
基礎研究と違い、私の研究室で進める研究は、マテリアルサイエンスと材料開発です。材料をいかに作って、それを世の中に還元するような基礎を構築するかというのを研究の対象にしているので、出口をいくら考えていても絵に描いた餅で終らせる可能性が非常に高いです。本当に何かしら実用化につながってもらわないといけないことを考えると、共同研究先の企業を探すのが、とても大変です。
このインタビューもそうですし、月曜日には産学連携で講演致しますが、そういう場でアピールして、少しでも企業側が私のことを引っ張り上げてくれる為の種をまく必要があると思っています。そこが一番大変ですね。
--そういう話で言いますと、化粧品メーカーが、一つ組みたい先としてありますよね。
中路氏:もし興味を持っていただけるなら、そのニーズやもっと詳しい社会のニーズもお持ちでいるでしょうし、そういう情報なども交換しつつ、ちゃんとした材料にカスタマイズしていくというのは必要なので、化粧品メーカーさんが興味持ってくれるのは、嬉しいですね。
--そういう意味で、他の分野で言いますとどういったメーカーがありますか?
中路氏:今欲しいメーカーとしては、塗料メーカーがあります。今、海洋コーディング、船艇のコーティングに取り組んでいます。ポリマーの材料でO社と特許を出願しています。
船底塗装が、赤い理由は銅に由来します。この銅を徐放してフジツボや海藻類がつかないようにしていますが、これがもつのは3ヶ月だと言われています。
--3ヶ月しかないんですか。
中路氏:徐放しきったら終わりなので。拡散で出てくだけなので、3ヶ月経ったら効果がなくなり、フジツボなどがまた付き出します。船、特にタンカーでしたら、海に入ってだいたい1年で燃費が4倍になります。
--4倍も上がるんですか。
中路氏:1年経ったらフジツボがびっしりなんですって。それを改善するためにポリマー材料を作り、それを塗料に混ぜて塗って、フジツボも海藻類もつかないというようなコーティング材料の開発というのを今やっています。
元々私がやっていましたが、学生にやらせています。お金は学内の予算を取ってやっていますが、共同研究先を探しています。塗料メーカーなどが興味を持ってくれれば有難いです。
学会で、ある塗料メーカーの方に話を聞いたら、タンカーなどは、3年とか5年とか持たないといけないと言っていました。
一応論文も出していますが、1年以上は何もつかない表面はできています。ただ論文を出すためには、3年とか4年かけていられないので、1年での結果となっています。1年でも長いぐらいです。1年海水の中につけておいて、何もつかないということを確認したということです。これが3年、4年つかないかと言われると、それは長期に見ないとダメです。
--1年の傾向だけでは、いけないのでしょうか?
中路氏:そう、それ以上のエビデンスがないと言われると反論できませんし。ただ、我々の研究の中で、過酷な条件、つまり煮沸して表面状態を観察した結果もあります。
--加速試験というやつですね。
中路氏:そう、それでざっくりとした換算をおこなうと、2年強ぐらいまで表面は安定という結果になりました。タンパク質や菌類などがつかないというのを確認しているので、多分いけると思っています。興味を持つメーカーがいれば、是非とも共同研究はしたいところです。共同研究先を探すために、私どもは学会などで発表しますけれど、この頃、企業さんは学会には聞きに来なくなってきています。
--そうなんですか。
中路氏:少なくなってきましたね。ただ、唯一企業さんと繋がれるのが、高分子学会で言えば11月に開催されているポリマー材料フォーラムという学会です。そこは企業向けの学会なので来られますが、学術会議にはあまり来られません。
高分子学会も、バイオマテリアル学会ももう賛助会員がどんどん減っています。聞くところでは、基礎研究であまり出口に近くないからと耳にしました。
--昔は、ネタやアイディア探しに行っていましたよ。
中路氏:昔はそうでした。私が学生の頃には、企業さんが多かったですが今は違います。あまり先行投資されないのかもしれません。
--そうなんですね。
中路氏:企業さんとの繋がりという面では、難しいというのがありますね。ですから、産学連携と繋がっていることは、大事になります。
--お話を聞いてますと、海洋コーティングは色々なところに応用できそうな形ですね。企業側としても実際のニーズに合わせて色々やりやすく、商品化しやすいということはあるかもしれませんね。
中路氏:私の独りよがりかもしれませんけど、海洋コーティングは、出口のことを少しでも考えて研究設計しているので、繋がりやすいと思っていただけるのかなと思ったりはしています。出口をどこに設定してそのために何をするのかを逆算して考えていくというのは、結構大事にしてますね。
--具体的には、どういう形で指導されていますか?
中路氏:学生が研究室に入ってきて最初に言うのは、「自分が3年後、どういうところで生きていきたいのか」というのを考えることです。
本当は、10年先から逆算して考えてほしいのですが、まだまだ分かっていないことですから、3年後に何をしていて、達成するためにはどんな能力持っていないと達成できないかを考えると、その能力をつけるために何をしないとダメかということを3年、1年半、1年、3ヶ月、1ヶ月、1週間後という具合に期間を区切って、4年生の時に計画を立てさせます。学習計画書まで作らせます。
最初は嫌がっていましたが、M1になると学習計画書を書いていないとやっている気がしないと言っていますので、多分先を見越して逆算して考える事が出来ているのだと思います。
それは研究も同じで、出口を考えて、出口のためにどんな材料が必要なのかを考えるのと全く一緒です。考え方は全部同じで、その方向性が違うだけということを言っています。
--学生がやりたいというテーマに関しても、出口を先に考えさせるのですね。
中路氏:そう、まずその研究やりたいのだったら、出口を考える。逆算したらこういう材料開発になりますよね、ということは教えます。
--はねたりとかしたり、提出し直しということもありますか?
中路氏:いや、どちらかと言うと、「こういう風なことを考えるとこういかない」と言います。私たちが学生の時代は、はねたりはありましたが、今はやりません。
--そうですよね。
中路氏:結果的に、はねてるのと一緒にはなりますが、「こうしたら良いのでは?」そういう風に伝えます。そこは気を遣います。
学生がいなかった方が多分研究は進んでると思います。自分1人で12テーマは無理ですが、2〜3テーマとかでしたら、学生がいなかったら100倍ぐらい早く進んでると思います。
一方で、今面白いなと思う研究を13テーマ動かすことが可能なのは、学生がいてくれるからで、ありがたいと思っています。
私は、学生に還元するために、成長するための元を提供しないとダメと思っていますので、企業と交わる機会などを与えたり、自分の技術を伝授したりしています。
--最後に産学研究を進めようとしている若い研究者へのアドバイスをお願いします。
中路氏:「産学研究を進めようとしている」ということでしたら、「世の中を知ること」が一番かなと思います。ニーズですよね。ネットなどでも知れますが、限界があります。そうなると企業とつながることが近道となります。研究者が一足飛びに企業と繋がることはほぼ難しく、その窓口となるのが産学連携本部だと思っています。
産学連携本部は、情報をたくさん持っています。それに特化されてる部署なので、いち早くつながっておくべきだとは思います。それが一番大きいと思っています。
私も学位取り立ての頃は、どうやって研究費を稼いでこようかと思い悩みました。共同研究を進めて一個大きな仕事をするというのが、一番の近道かもしれません。
その間に自分が国の研究費を獲得できるように修行を続ける。共同研究で1個大きな花が咲くぐらいに、3年の間に自分で研究費を獲得できるようになれば良いのかなというのはありますね。
私は29歳で学位を取り、その後、同じ研究室でポスドクを2年続けさせてもらって、その間に最初の若手研究Bの競争的研究費をとって、外に出ました。そういう風に養ってくれる先生がいるなら良いですが、学位取得後すぐに独立するというのが良いかというと分かりません。大学を講座制に戻した方がよいと思っているくらいですから。
独立した研究室になると、自分でお金を稼いでこないといけません。すごく大変だと思います。もし繋がりがあるという事であれば、最初に自分の研究に関連して企業と共同研究を進め、企業が求める成果を出しつつ、国の競争的研究費を取りに行く。
若い人にとっては、企業と共同研究が終わるまでに修行して取ってくるという形でも良いのではないかとは思ったりはしますね。ですから、共同研究はやるべきだとは思いますね。それで自分がどれだけ小さい人間かということもわかるので。
基本的に、大学教員は小さいコミュニティにいるので、世間知らずだと思っています。ですから、企業と繋がって世の中でこんなニーズがあって、今こんなことが求められてるということを常に吸収しとかないと絶対に乗り遅れます。
今の若い人、私の1世代後の研究者は、そこら辺をしっかり頭の片隅に置いておかないと、食いっぱくれてしまう、研究者としてやっていけないんじゃないかなと思ったりしますね。
研究者は決して偉くはなく、ただ単に色々な知識を持っていて、それを具現化できるスキルがあるだけだと思っています。
--大学を卒業してからずっと大学の中にいらっしゃる先生と外部の企業から大学にいらした先生もいますね。2人2種類で結構マインドが違いますよね。
中路氏:全然違うと思いますね。
--一旦外に出て民間企業から戻ってこられた先生は、物わかりがよいというか、共同研究や色々な研究の進め方もうまくやっていらっしゃる印象を持ちますね。
中路氏:ですから、ちゃんとそういう風なマインドを持たないといけないと思います。私は、大学から外部に出たことはありませんが、テニュアトラック時代に、O社に2ヶ月、N社に3ヶ月、T社に1ヶ月、インターンシップで延べ6ヶ月行かせてもらいました。本当に有難かったです。
学生時代にもインターンシップは行ってましたけど、テニュアトラックの時が一番多かったですね。年に1回、1か月はどこかに行ってました。共同研究している企業には、1ヶ月、2ヶ月、1週間でもいいから一緒にやりましょうと言って、外に出ていました。
研究室のセットアップに、O社などで学んだことがたくさん入っています。色々な研究室や施設で見てきて、良かったところは研究室に取り入れています。
--民間企業の良いところを学んでいるんですね。
中路氏:そうですね。良いところは、どんどん取り入れてきた感じですね。テニュアトラック時代には、1、2週間ですが、学生のインターンシップに私も一緒について行ってました。
--フットワークが軽いですね。
中路氏:大学の仕事は大丈夫かと聞かれましたが、テニュアトラックの時はまだ授業を持ってませんでしたからね。
授業を持っている今でも、出ています。去年の秋は、T社さんに2週間ぐらい行っていますね。製造ラインに入ったりしました。
--ラインにも入る、すごいですね。
中路氏:実際ラインに入ってみて、教えてもらいました。実際に体験して分かることが非常に多いです。
学生にも、できる限りインターンシップに参加するように言っています。
インターンシップには、4年生の間に1回行ってこいと言っています。普通は、修士にいくと決まったら、行かない傾向にあるようですが、それではいけないと思うんですよ。M1の時に企業を見に行くっていうのと、4年の時に1回見に行っているのとでは、4年からM1までの研究生活の中でのマインドが変わってきます。
社会では、こういう人材を求めてるから、こういう風な人間にならないといけない、こう
いうことを目指さないといけないというのを知っているだけでも、成長が全然違います。
インターンに行くべきだと思っているので、教員になった後でもインターンシップなどは、かなり行きました。インターン先では、学生より喜んで実験してましたからね。
私自身大学にずっといましたから、社会のことを何も知らないという負い目もあって、学生を教育する立場という意味でも、少しでも知っておこうと思っています。ですからそこは大切にしています。
企業の人事さんの中には、就職担当の先生のところに行った後、先生方に挨拶に来られる方がいらっしゃいますが、私はその方と、絶対に1時間ぐらい話します。それで仲良くなって、気心が知れて、企業によっては、今は就職担当の先生ではなく、直接私を訪ねてきてくれます。
研究室で誰か1人もらえませんかという話があれば、社会のニーズを聞きつつ学生の中に合いそうな人いたら紹介して、マッチングできれば入ってもらうという考えでいます。
今年もうちのM1の学生で、まだ6月ですが、大手医療機器メーカーへの就職活動が進んでいます。
--それは、早いですね。
中路氏:それで、その大手医療機器メーカーが、企業研修やると言われたので、私も一緒に行きたいと言いましたら、流石にダメだと言われました。そこの中央研究所に行ってみたかったのに。
別の企業さんでは、社会のことを知ろうとする私の取り組みについてお話をすると、秋口に某製薬メーカーの研究所からの招待講演で話する代わりに、研究所と工場を見学させてもらう約束を取り付けました。
そうなると共同研究になるかもしれないということで、多分見せられないところと見せられる所は選定しているのだと思いますが、MTA契約を結ばないといけないということになりました。
--製造現場を見るということは、大変なことなんですね。
中路氏:製造現場を知っておけば、製造ラインに持っていっても耐えられるような作業、製造工程をきちんと元から考えることが可能です。そうすればシステマティックにする時に悩まなくて済みます。ですから製造現場を見ておくのは、絶対必要だと私は思っています。
--それがゴールから考えるということですね。
中路氏:その通りです。
--企業のラインには、見せてはいけないラインがありますよね。
中路氏:そうなんです。単純に見えるんですけど、緻密らしいですね。
--見学用のラインが別にあると思いますが、そこ以外のところを見たいと言われたのではありませんか?
中路氏:機密が多いのでといわれましたね。
商品化する時は、研究室みたいに人が1から10まで作るわけではないので、そうなると機械製造に変えやすい、もともとの作り方とかいうのが必要になります。これには、製造過程をこちらが知っているか知っていないかで、大きく違ってくると思っています。
少しでも近づけておくということを大切にしています。素人が近づける程度ですが、それでも0か0.1かでだいぶ違うと私は思っています。
若手の人は、研究費を稼いでくるのもそうですし、共同研究するのもそうですけど、フットワークが軽いのは今のうちなので、大学だけではなく色々な企業に出向というか、内地留学、見学でもよいですから、知識を吸収すべきだとは思います。
私も偉そうなこと言える立場ではありませんが、30代の人たちにはそういうことを気にしながらやってほしいなとは思います。
研究者マインドがガラッと変わる世代なので。企業の歯車ということではなく、できないところとできるところの分別をきちんと分けて、やってもできないところは協同して、企業なり共同研究者なりという風な形でネットワークを作って、それできちんと出口があるようなことをすべきと思います。
研究のための研究とか、論文のための研究とかではなく、人知れず役に立っているとか、そういう風なことをきちんと目指す。出口を設定しない研究はやらない。「何のためにこの研究をやるのか」このことを大切にして研究はしてほしいですね。
--本日はお忙しい中、ありがとうございました。